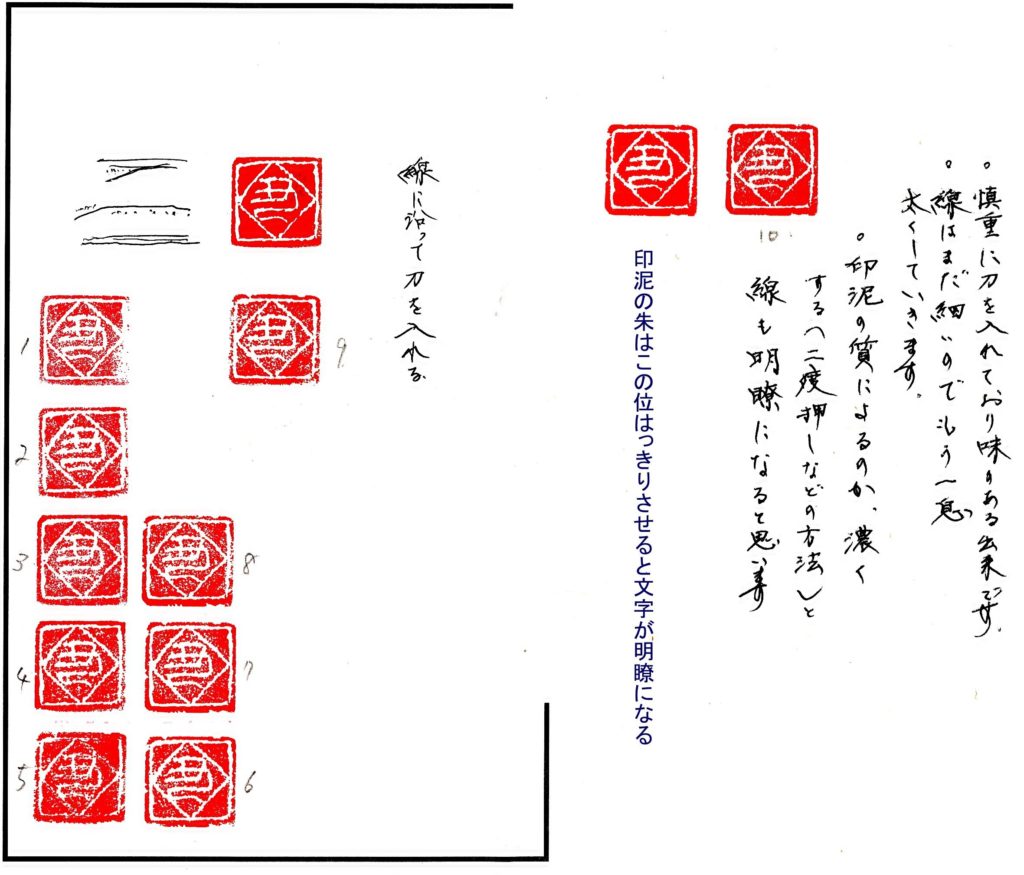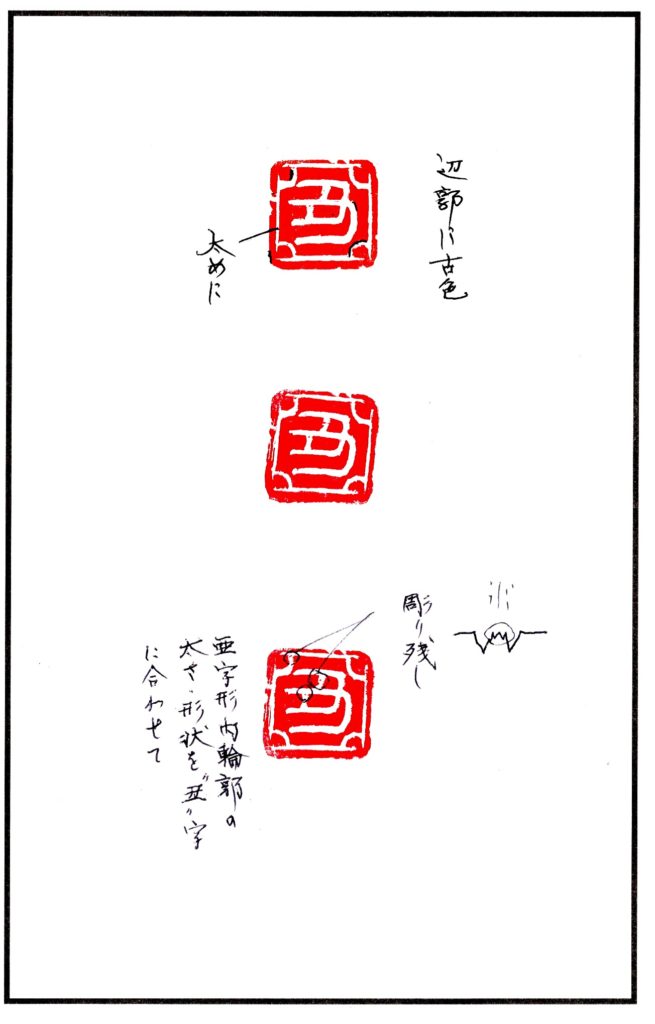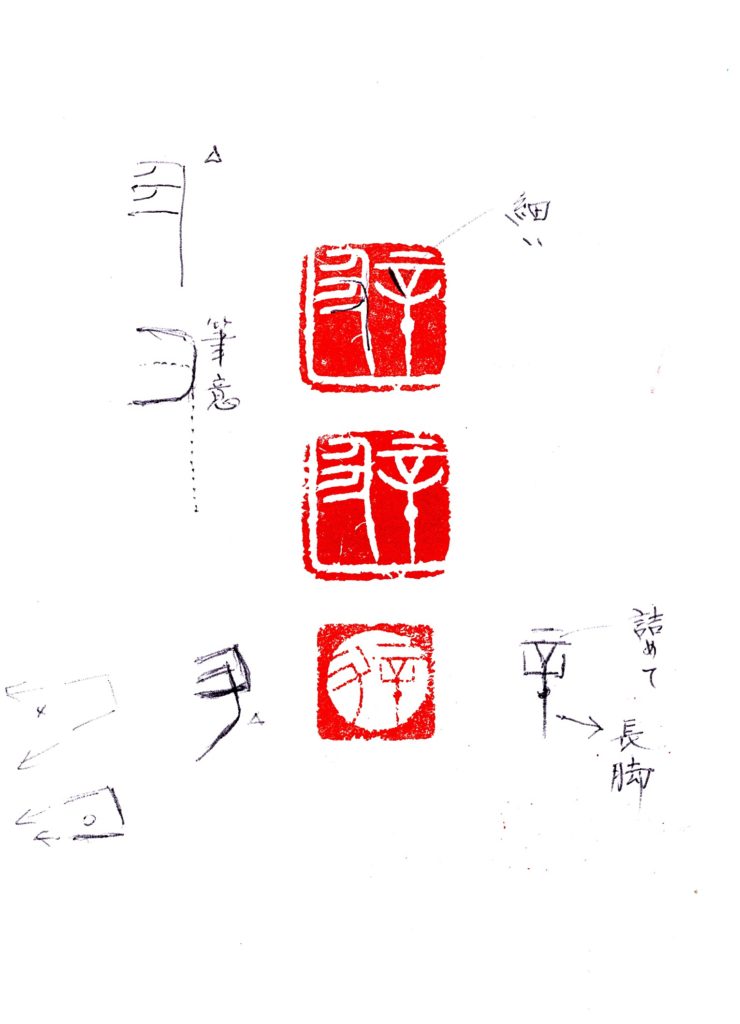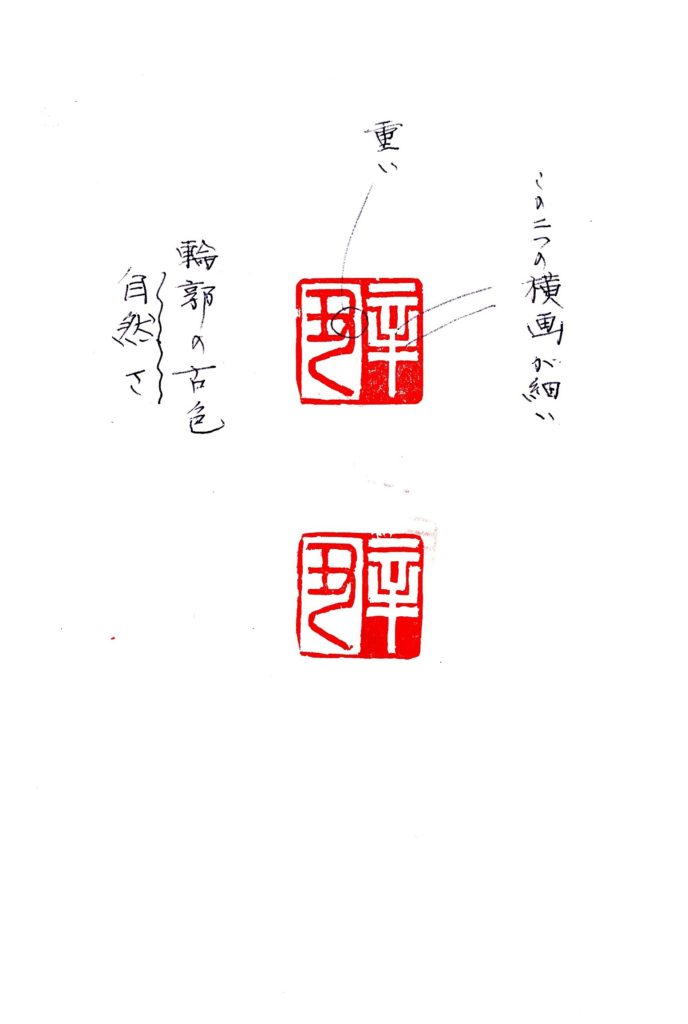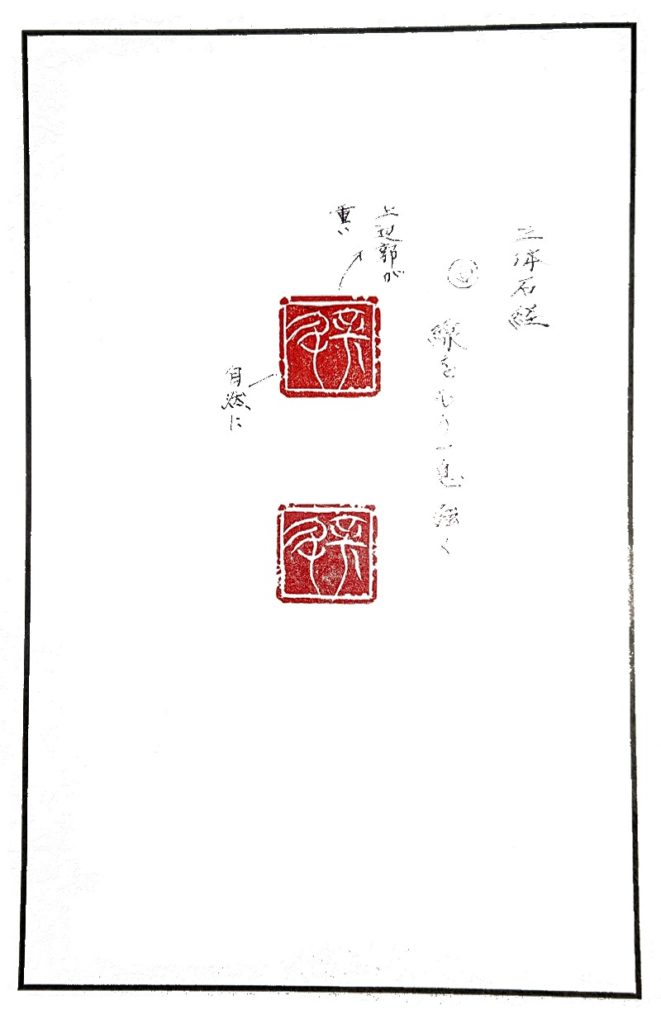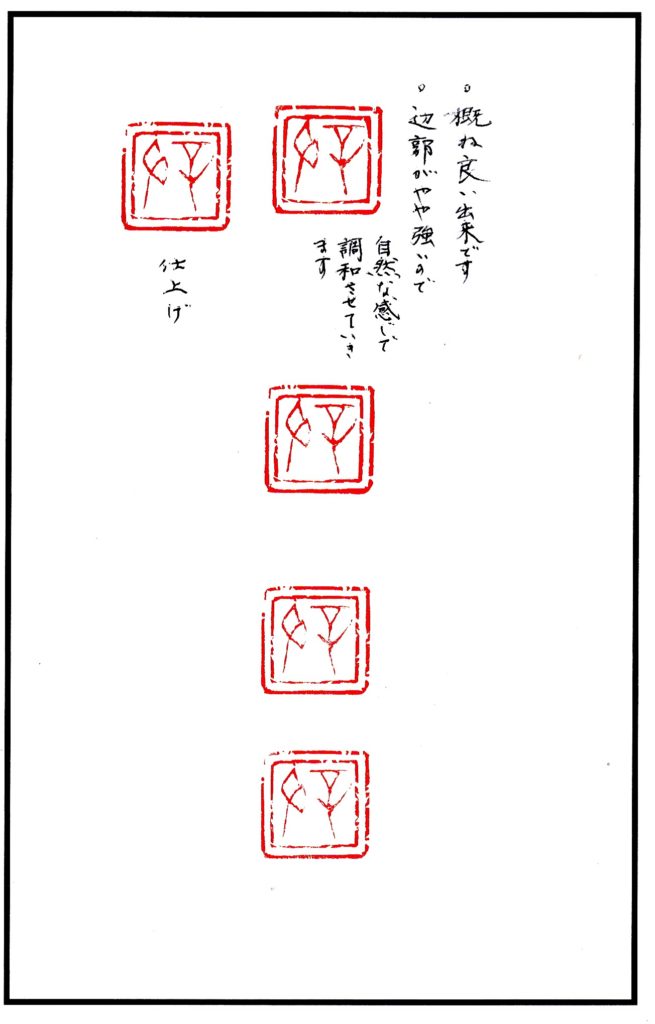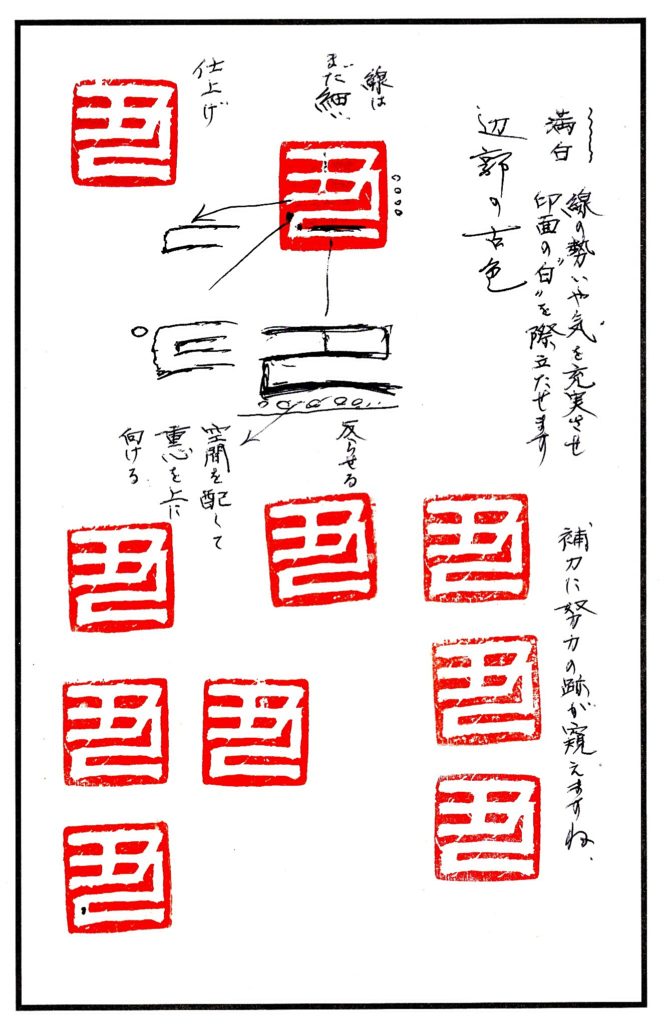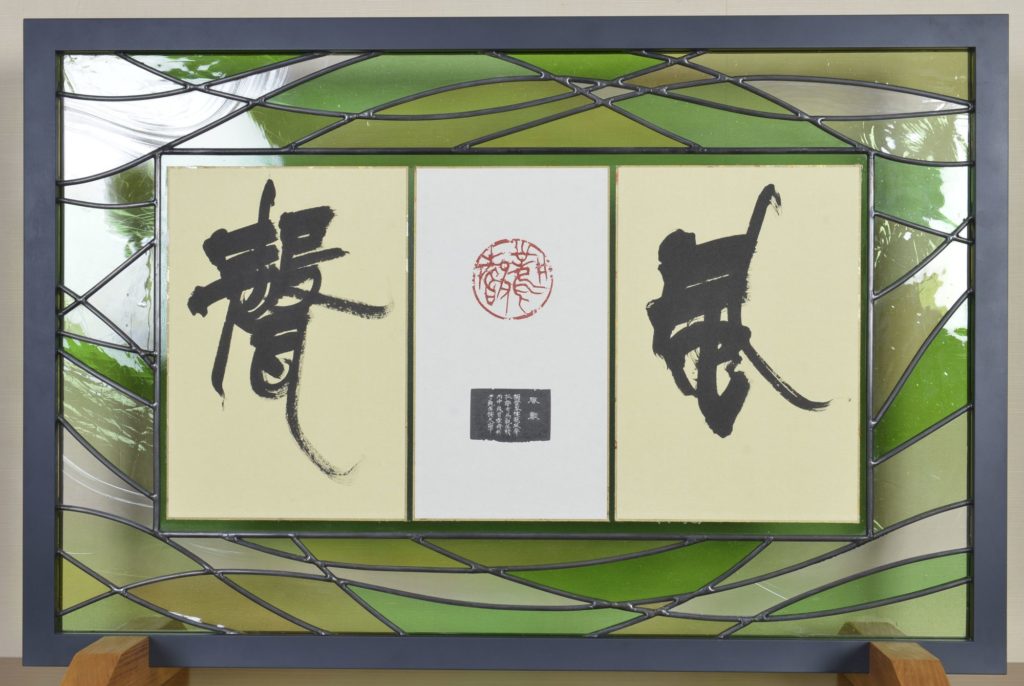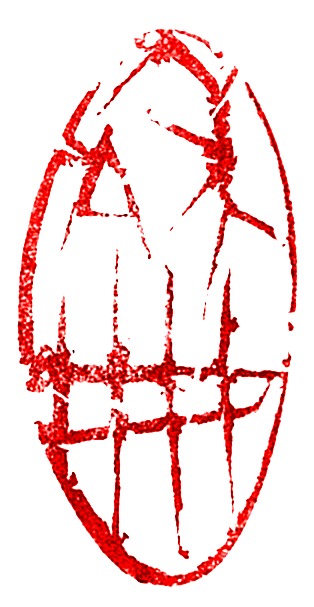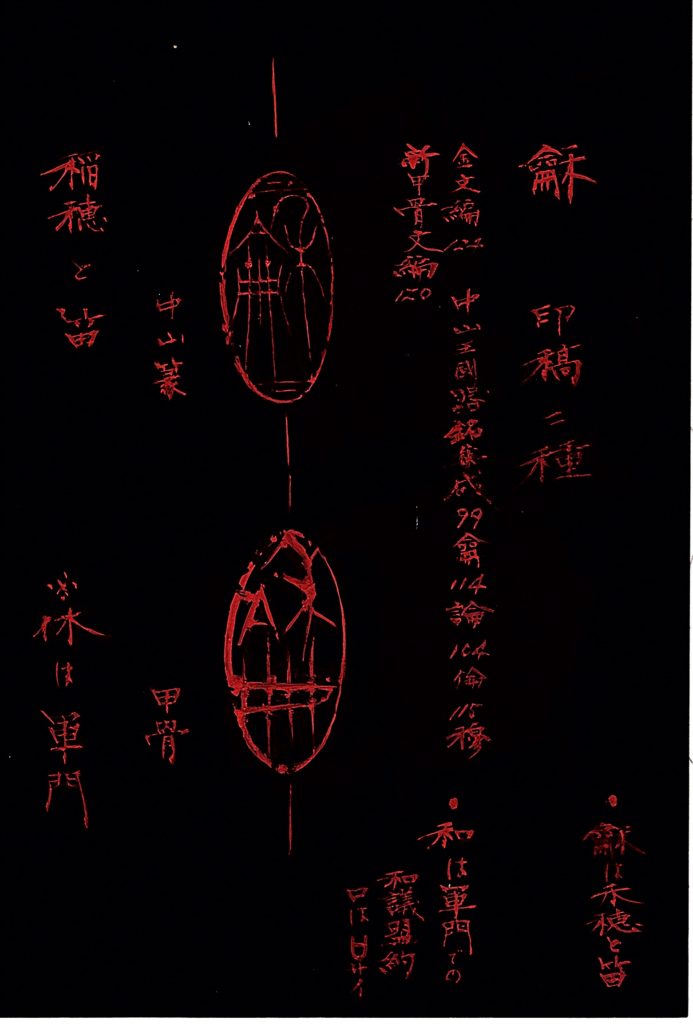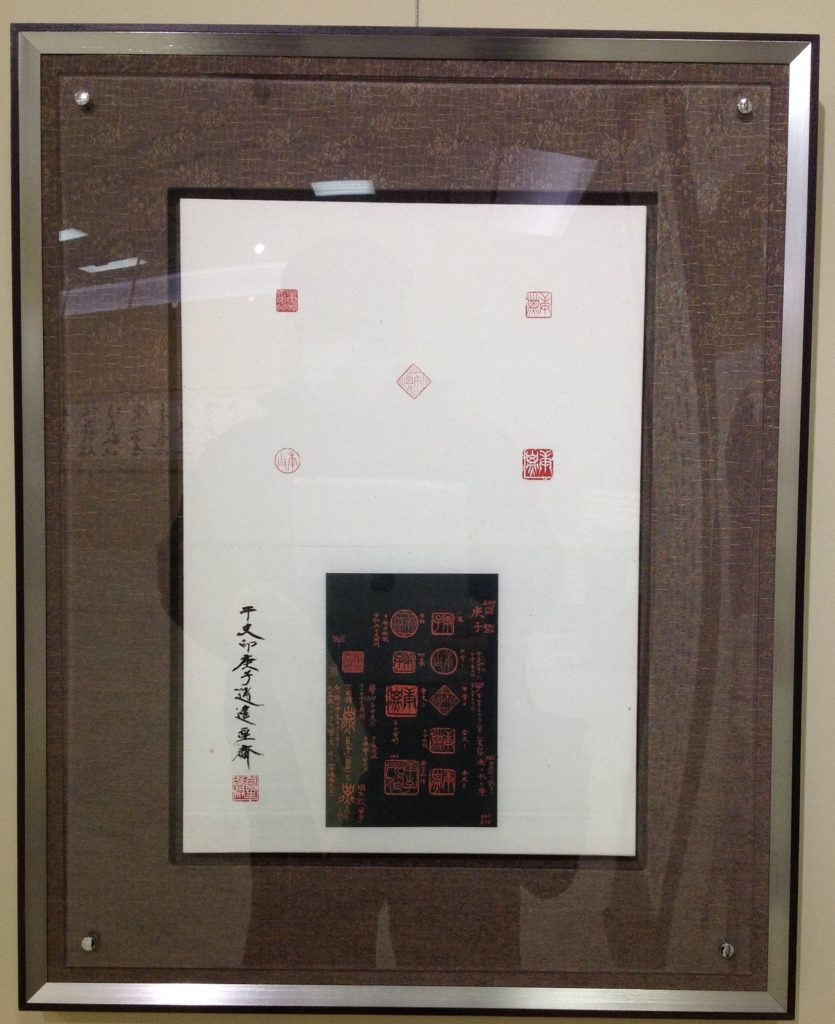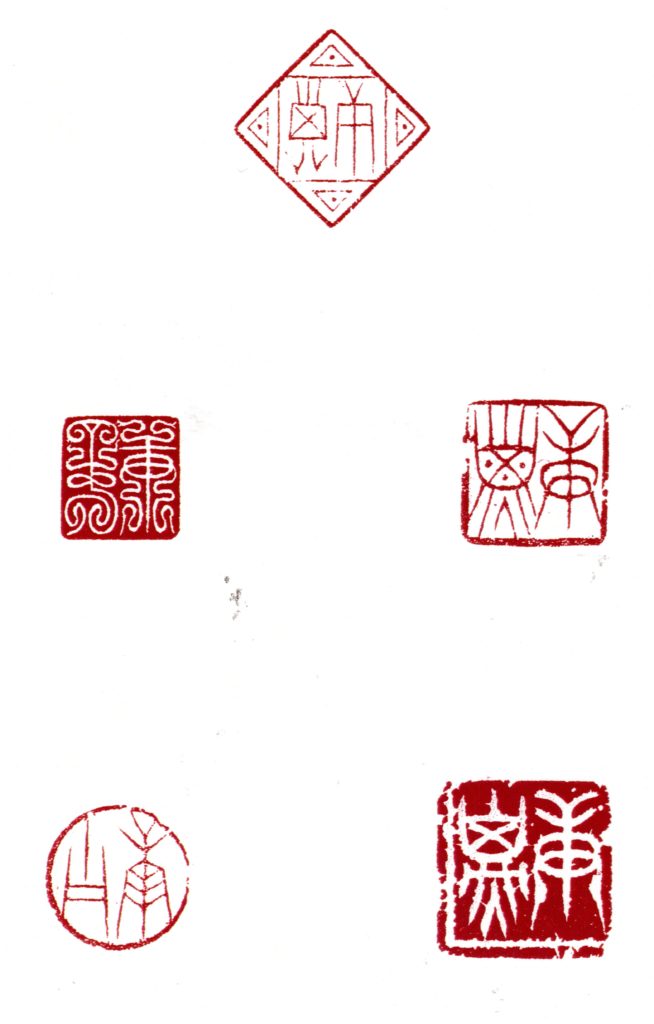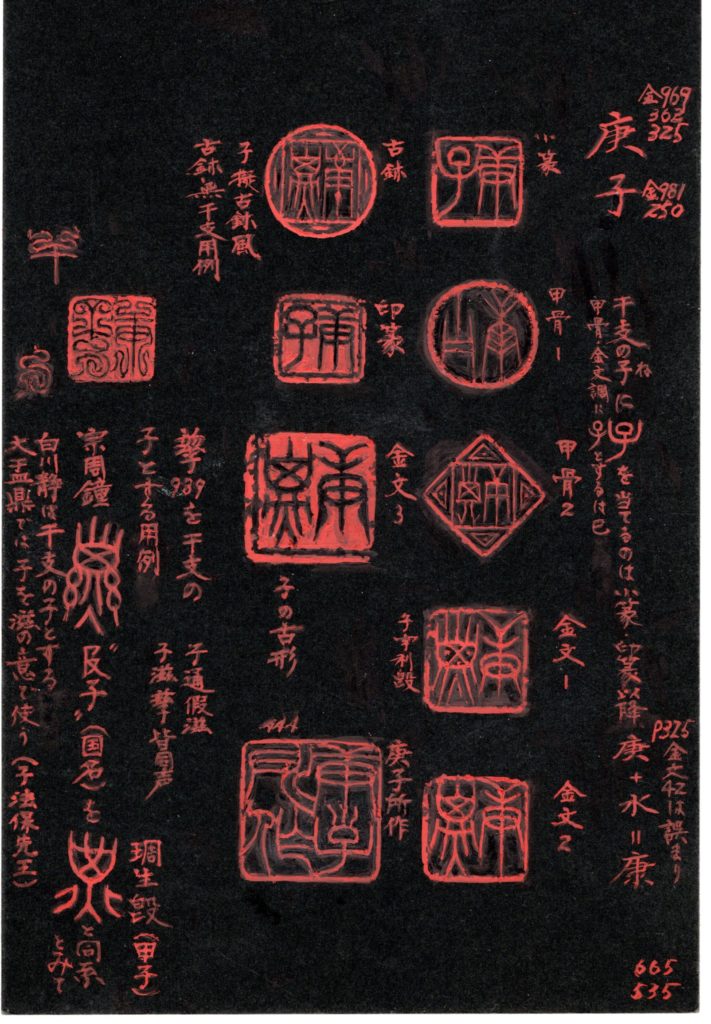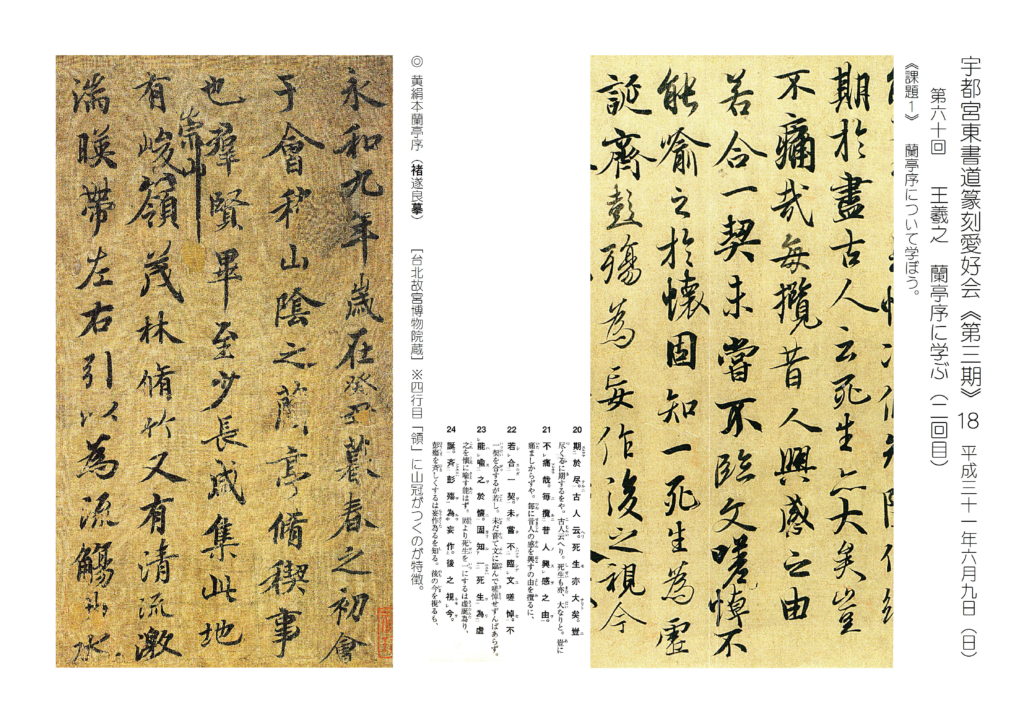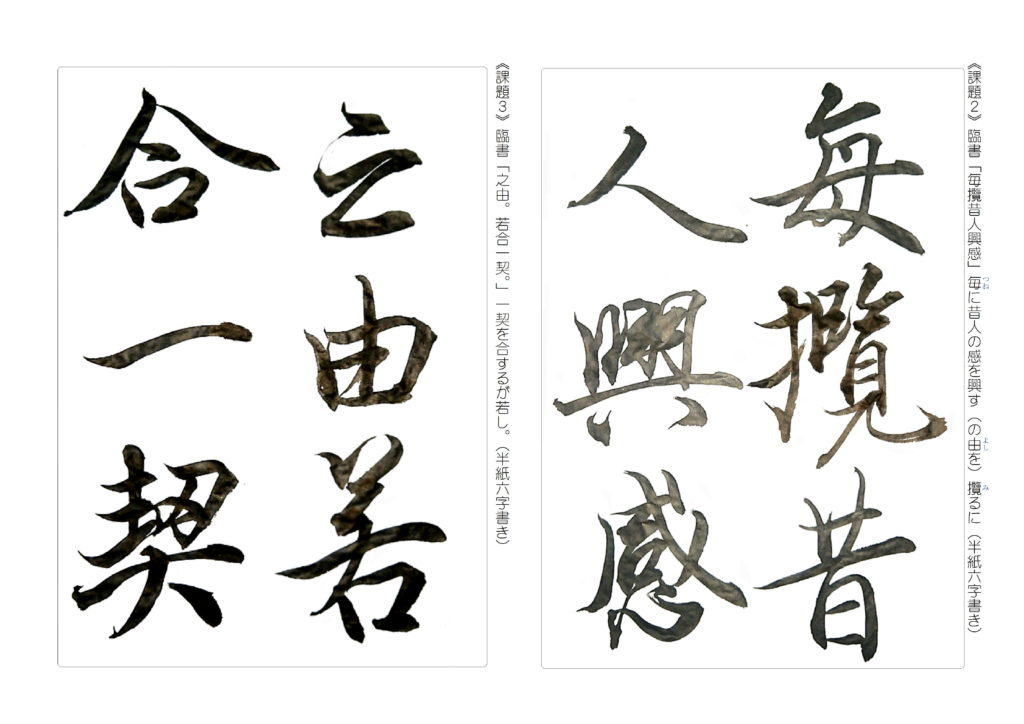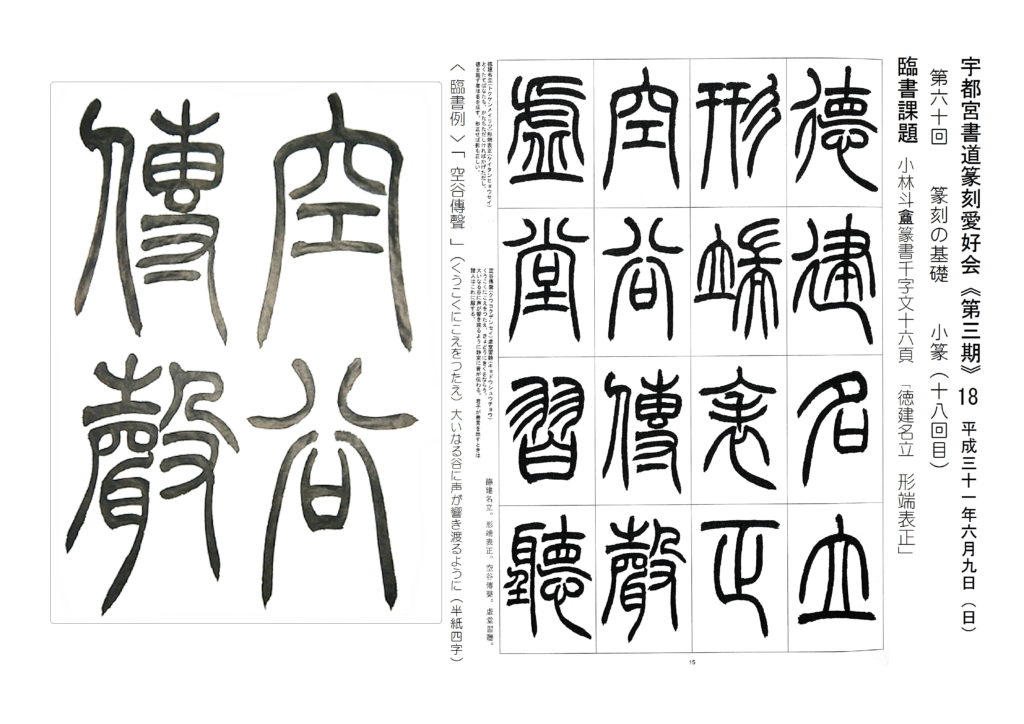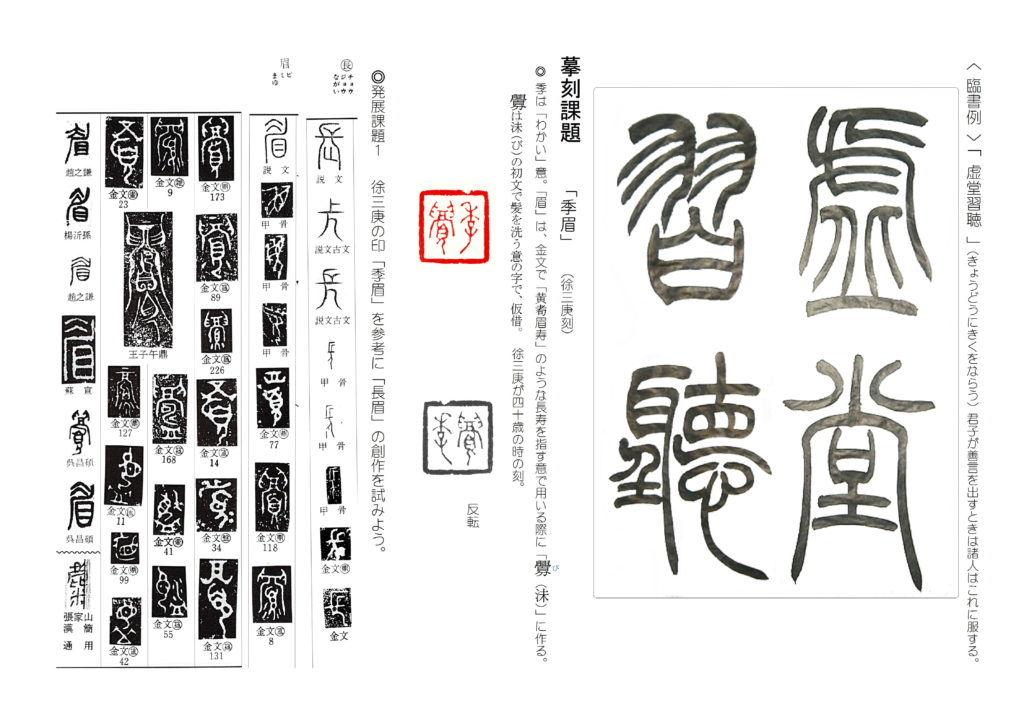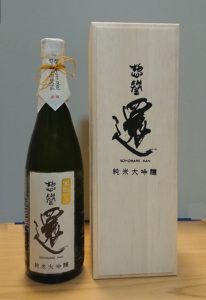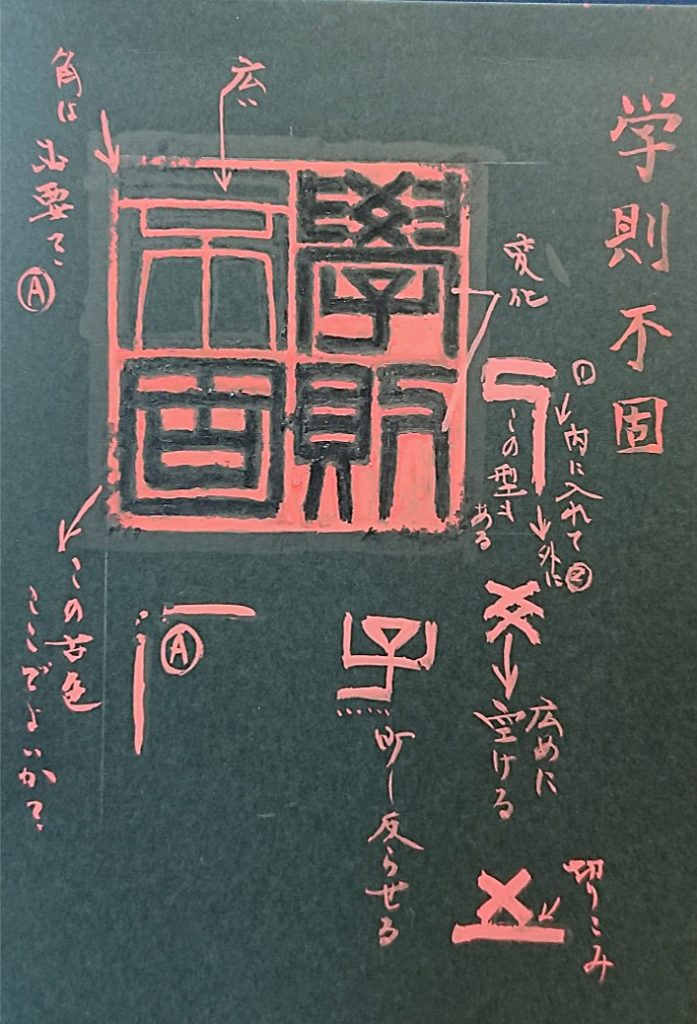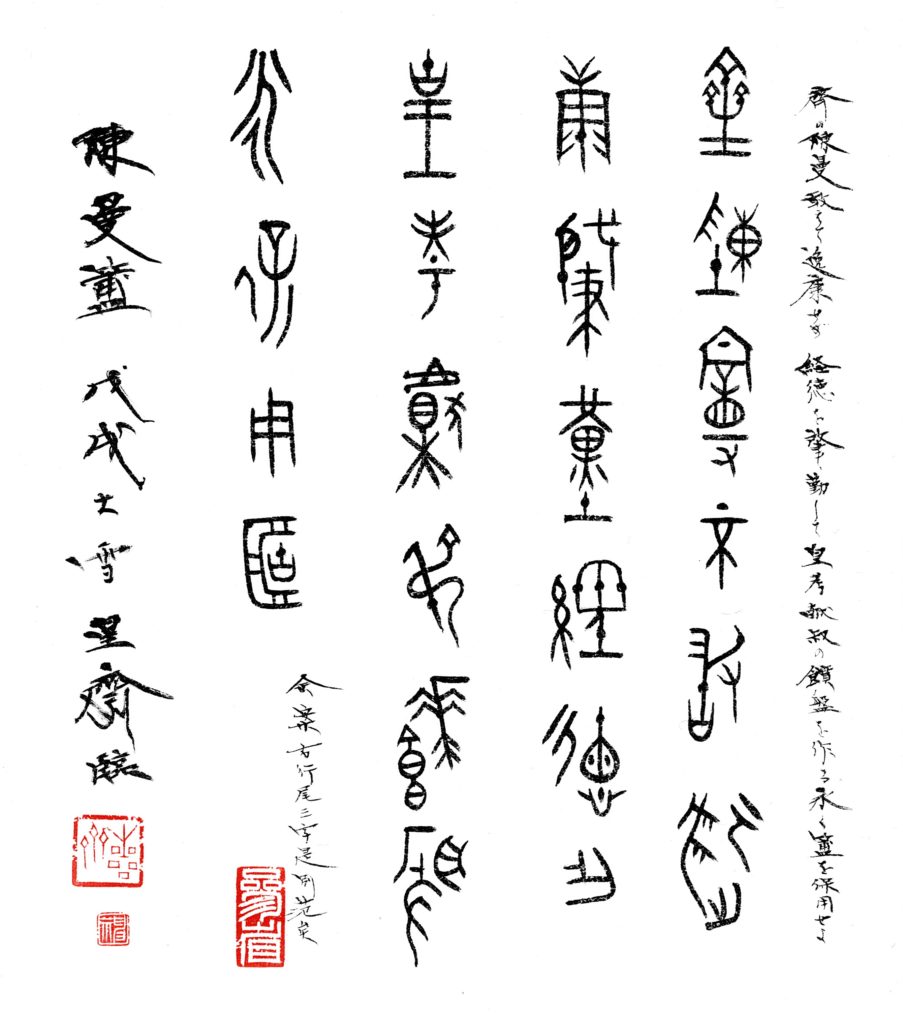開催要項
生誕100年記念 白川静『文字講話』に学ぶ、干支印を彫ってみよう案内受講された方の人数
9月27日(日) 白川静『文字講話』に学ぶ (1日目) 51名
10月11日(日) 白川静『文字講話』に学ぶ (2日目) 46名
10月17日(土) 文字講話実技編 篆刻講座「干支印を彫ってみよう」 22名
使用したDVD
白川静「文字講話」DVD完全収録版
第11巻「第二十一話 甲骨文について」・「第二十二話 金文について(Ⅰ)」
解説用パワーポイント
今回のために作成したもの 3種
配付資料
1.白川静「文字講話」に学ぶ
第1回甲骨文について 「白川静 続文字講話」(平凡社)
第2回金文について 同
2.篆刻講座「干支印を彫ってみよう」
パワーポイントのスライドを印刷したもの
※熱心に聴講していただきありがとうございました。
『文字講話』のための参考資料(PowerPoint)の一部をご紹介します。
(矢印をクリックすると閲覧できます。)
文字講話解説用パワーポイント資料(一部)
次は2日目 『金文について』解説資料(PowerPoint)です。
白川静 文字講話に学ぶ 金文について プレゼンテーション2
[会場風景]



篆刻講座「干支印を彫ってみよう」テキスト(PowerPoint)を紹介します。
(矢印をクリックすると閲覧できます。)
令和2年篆刻講座干支印でおしゃれな年賀状作り
[会場風景]

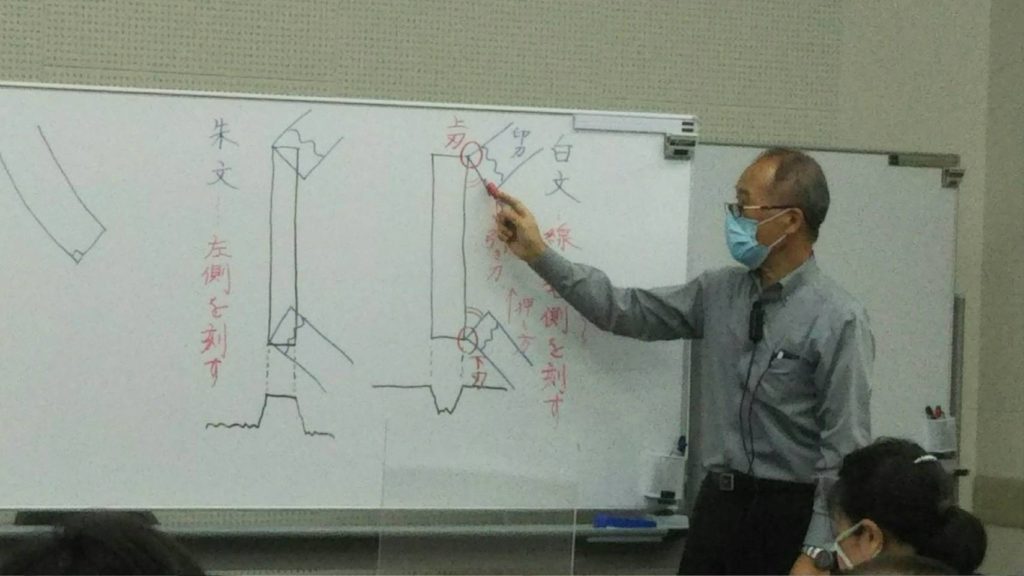


[参考印稿]
l¥.pptx
[受講者の印稿・印影と添削](例)